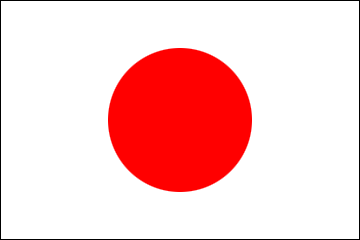ユネスコの主な事業
教育
●持続可能な開発目標(SDGs) の推進
持続可能な開発目標(SDGs) とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として、2015年9月に国連サミットにおいて全会一致で採択された2030年までの国際開発目標です。先進国を含む国際社会全体の開発目標として、2030年を期限とする包括的な17の目標が設定されており、ユネスコはゴール4(教育)の主導機関に位置付けられています。
SDG4を達成するために、ユネスコは識字学習や職業技術教育・訓練の促進、「高等教育の資格の承認に関する世界規約」(2019年)(日本は2022年9月13日に締結、2023年3月5日発効)の作成等高等教育の推進、教員の能力開発、ICT環境の整備等に力を入れています。また優先課題としてのアフリカにおける教育のアクセスの向上やコロナ禍後の女子教育の強化を含めたジェンダー平等にも取り組んでいます。
●持続可能な開発のための教育(ESD)の推進
持続可能な開発のための教育(ESD)とは、人類が様々な課題を克服し、持続可能な発展を遂げていくために、人々の価値観や行動の変容をもたらす教育です。現在は、2020年~2030年におけるESDの国際的な実施枠組み「持続可能な開発のための教育:SDGs実現に向けて(ESD for 2030)」に基づきESDが推進されています。
●ユネスコスクール(ASPnet School)の推進
ASPnet(Associated Schools Network)は、ユネスコの理念を学校現場で実践するために昭和28(1953)年に発足した、国際的なネットワークです。加盟校同士が活発に交流し、生徒間・教師間で情報や体験を分かち合い、地球規模の諸問題に若者が対処できるような新しい教育内容や手法の開発、発展が目指されています。日本では、ASPnetへの加盟が承認された学校を、「ユネスコスクール」と呼んでいます。日本国内の加盟校数は、令和7年9月時点で1,083校となり、1か国当たりの加盟校数としては、世界最大となっています。
自然科学
●環境・生態学、地質学等
生態系の保全と持続可能な利活用の調和を目的に、保護・保全だけでなく自然と人間社会の共生のための取組として、「人間と生物圏(MAB)」計画を推進しており、その中で、生物圏保存地域(BR:日本では「エコパーク」と呼称)を認定しています(2025年12月現在、日本からは10件登録されています)。
また、地層、岩石、地形、火山、断層など、地質学的な遺産を保護し、研究に活用するとともに、自然と人間との関わりを理解する場所として整備し、科学教育や防災教育の場とするほか、新たな観光資源として地域の振興に生かすことを目的に「ユネスコ世界ジオパーク」の認定を行っています(2025年12月現在、日本からは10件登録されています)。
●水科学の推進
ユネスコの国際水文学計画(IHP)では、陸域における淡水資源管理、水災害等予防、水にかかる紛争への対策、水にかかる総合的な研究等の事業を実施しています。国連における水科学に関する関連機関とともに、毎年「世界水発展報告書」をとりまとめ、水の問題に関する基礎的なデータを提供しています。
●オープンサイエンスの推進
ユネスコでは、近年のオープンサイエンスの重要性の高まりを受けて、オープンサイエンスの政策と実践のための国際的な枠組みを提供するため、「オープンサイエンスに関する勧告」(2021年)をまとめています。
●政府間海洋学委員会(IOC)
IOCは、地球規模での海洋学に関する知識、理解増進のための科学的調査の推進を図ることを目的とした海洋科学調査及び研究活動に係る唯一の国際機関で、津波早期警戒システムの整備、全球海洋観測システムの構築、国際海洋データ・情報交換システムの運用、教育訓練・能力開発・技術移転、「持続可能な開発のための国連海洋科学の10年」の推進などを行っています。このうち、津波早期警戒システムについては、津波研究・対策への日本の豊富な経験を背景に、太平洋地域津波警戒・減災システムにおける実績を基に世界各地の海洋にシステムを構築すべく主導的役割を果たしています。
人文・社会科学
ユネスコの国際生命倫理委員会(IBC)及び政府間生命倫理委員会(IGBC)では、生命倫理に関する国際的な基準やルールの検討を行っており、これまで、「ヒトゲノムと人権に関する世界宣言」(1997年)、「ヒト遺伝情報に関する国際宣言」(2003年)、「生命倫理と人権に関する世界宣言」(2005年)などをとりまとめています 。
また、科学的知識と技術の倫理に関する世界委員会(COMEST)では、生命倫理以外の科学倫理の問題について諸問題を検討しており、近年では、量子コンピュータ技術や宇宙探査に係る倫理問題の議論などを行っています。
これらの委員会での検討に基づき、新興技術に対する倫理的側面からの勧告として、「人工知能(AI)倫理に関する勧告」(2021年)や「ニューロテクノロジーの倫理に関する勧告」(2025年)がユネスコ総会で採択されています。
●スポーツ
ユネスコでは、体育・スポーツ担当大臣等国際会議(MINEPS)を主宰しており、加盟国・準加盟地域のスポーツ担当大臣等が集まり、スポーツにおける国際的重要課題について議論し、実行指向型の提言を取りまとめています。2023年にはアゼルバイジャン・バクーにて同会議が開催されました。また、ユネスコには同会議への提言等を検討する体育・スポーツ政府間委員会(CIGEPS)が設けられています。その他、ドーピングの撲滅を目指し、国内及び世界レベルの協力活動を推進・強化するため、2005年10月のユネスコ総会では、「スポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約」が採択されています。
文化
「世界遺産条約」は、正式には「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」といい、文化遺産や自然遺産を人類全体のための遺産として損傷、破壊などの脅威から保護し、保存していくために、国際的な協力及び援助の体制を確立することを目的とした条約です。
「世界遺産」とは、世界遺産条約に基づいて作成される「世界遺産一覧表」に記載されている物件のことで、建造物や遺跡などの「文化遺産」、自然地域などの「自然遺産」、文化と自然の両方の要素を兼ね備えた「複合遺産」の3種類があります。
2025年12月現在、1248件(文化遺産972件、自然遺産235件、複合遺産41件)の世界遺産が記載されており、このうち日本の世界遺産は26件(文化遺産21件、自然遺産5件)です。
●無形文化遺産保護条約
2003年のユネスコ総会において、伝統的舞踊、音楽、演劇、工芸技術、祭礼等の無形文化遺産を消滅の危機から保護し、次世代へと伝えていくことを目的とした「無形文化遺産の保護に関する条約」が採択されました。 「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」として、2025年12月現在、日本からは、歌舞伎や和紙、和食、伝統的酒造りなど 23件が登録されています。
●その他のユネスコ文化関係条約
ユネスコが作成した文化に関する諸条約は、主に6つあります。日本が締結している上記の「世界遺産条約」(1972年条約)や「無形文化遺産保護条約」(2003年条約)のほか、「文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約」(文化財不法輸出入等禁止条約(1970年条約))や、「武力紛争の際の文化財の保護に関する条約」(1954年ハーグ条約)及び関連二議定書(1954年及び1999年)があります。また、日本が未締結の条約としては、「文化的表現の多様性の保護及び促進に関する条約」(2005年条約)や「水中文化遺産の保護に関する条約」(2001年条約)があります。ユネスコはこうした条約の実施に関する支援及び促進を通じて文化の保護に精力的に取り組んでいます。
●ユネスコ創造都市ネットワーク
文学、映画、音楽、芸術などの分野において、都市間でパートナーシップを結び相互に経験・知識の共有を図り、またその国際的なネットワークを活用して国内・国際市場における文化的産物の普及を促進し、文化産業の強化による都市の活性化及び文化多様性への理解増進を図る事業として、 創造都市ネットワーク事業を推進しています。分野は文学、映画、音楽、クラフト&フォークアート、デザイン、メディア・アートと食文化の7つあり、2025年12月現在、日本からは、7分野で12都市(神戸市、名古屋市、金沢市、札幌市、鶴岡市、浜松市、篠山市、山形市、旭川市、臼杵市、岡山市、越前市)が加盟しています。