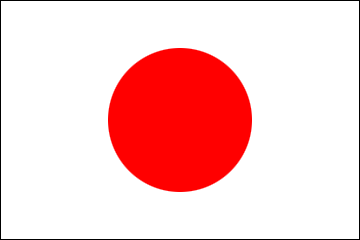気候変動/激甚化・頻発化する災害から世界の人々を守る~ユネスコ防災の挑戦~自然科学局防災課 安川課長寄稿
令和6年3月29日
 ユネスコ自然科学局防災課長 安川総一郎さん
ユネスコ自然科学局防災課長 安川総一郎さん
気候変動/激甚化・頻発化する災害から世界の人々を守る~ユネスコ防災の挑戦~
自然科学局防災課長の安川総一郎です。2013年に国土交通省から派遣され、2017年にユネスコ職員となりました。この11年弱、ユネスコパリ本部の自然科学局で防災の担当をしています。
ユネスコは(United Nations for Educational, Scientific and Cultural Organization)、所掌範囲が広く、具体的には教育、自然科学、海洋、文化、社会科学、コミュニケーション・情報、アフリカを専門とする局、政府間委員会が、総会により決定された中期計画(2022-2029)、プログラム・予算(2024-2025)にのっとって、各国のSDG、パリ協定、仙台防災枠組み等、国際枠組みの実施のサポートをしています。防災課では地震防災と各部局で行っている防災業務の取りまとめをしており、国連や外部機関に対する防災の窓口となっています。
ユネスコで防災の仕事をしているというと、ほぼすべての方からユネスコで防災の業務をやっているなんて知らなかったといわれます。ユネスコというと日本では世界遺産が有名ですが、防災分野でも、他の国連機関と協力しながら防災、気候変動対応業務を行っています。この投稿でユネスコの防災について知ってもらえると幸いです。例えば国連事務総長が2027年までに地球上の人全員が自然災害早期警報にアクセスできるようにするという計画を2022年に発表しましたが、ユネスコはその計画のうち観測と警報という科学的な分野について、世界気象機関(WMO)、国連開発計画(UNDP)、国連環境計画(UNEP)とともに担当をしています。
我々は他機関と比べいくつかの点で特徴があると考えています。一つ目は所掌範囲が広いので分野横断的な防災の取り組みが可能となっています。例えば、学校カリキュラムの中で気候変動等について学ぶという防災教育や学校建物の耐震性向上といった科学的な観点からの防災を一つのプロジェクトで行うことが可能ですし、気候変動等の影響を受けている世界遺産等の文化遺産の適切な保護を行うことも可能です。(multi-disciplinary approachといいます)。
2つ目は幅広い災害を取り扱っていることです。ともすれば、洪水・渇水といった気候変動に伴う災害ばかり注目が集まってしまいますが、ユネスコでは気象関連災害だけでなく、津波、地震、土砂災害、火山など地質関連の災害にも専門のチームが存在しますし、これらを統合的に対応することも可能です。(multi-hazards approachといいます)。最後に、様々なステークホルダーを巻き込んだ取り組みです。ユネスコは各国にユネスコ国内委員会という窓口が政府の中にあります(日本の場合は文部科学省)。また政府のほかにユネスコには多数の専門家委員会(例えば、海洋、水文、地質学、生物圏保護等)、ユネスコチェア・センタープログラム(日本では、京都大学、神戸大学、立命館大学、島根大学、大阪大学、岡山大学、長岡技術大学等)を通じて外部の専門機関と協力関係を結んで、学術的に課題の解決を図っています。またユネスコではジェンダー、若者がユネスコの4大優先分野の2つとなっており(そのほかはアフリカ、小島嶼開発途上国)、政府、専門家に加え市民社会を巻き込みながらプロジェクトを実施しています(multi-stakeholders approachといいます)。
近年顕著な気候変動、都市への人口流入、災害リスクへの対策の遅れなどにより、自然災害による人的・物的被害が増えています。国連のデータでは、2000年から2019年までに130万の方がなくなり、40億人の方が影響を受け、3兆ドルの経済被害があったと報告されています。自然災害のうち約9割が気象に関する災害(ハリケーン、サイクロン、高潮、洪水、渇水、土砂災害)、死者の約6割が地殻に関する災害(地震、津波)であり、避けることができる被害を軽減するために防災はますます重要性を増しています。1ドルの事前対策を行うことで、15ドルの避けることができた被害や復興経費が削減されるといわれています(UNDRR)。
ユネスコでは具体的に8つの柱で各国支援をしており、具体的には1) 科学技術(人工知能等)を活用した防災、2) 早期警報、3) 建物の安全性(特に地震)、4) 教育分野の防災、5) 文化財等の防災、6) 自然を基盤とした防災、7) リスクガバナンス、8)災害後対応、となっています。
特に一つ目の科学技術を活用した防災ですが、ユネスコでは、近年AIやデジタルといった新たな技術が様々な地球規模解題解決に資するポテンシャルがあると考えており、科学技術やイノベーションを防災に取り入れています。近年、データの収集・クリーニング・分析の速度や容量が格段と上がっており、またAIも(特に日本で)防災への活用が試みられています。ユネスコでは防災スタートアップやAI 企業と意見交換をしながら、パイロットプロジェクトを通じてAIやイノベーションを防災分野に取りこむ努力をしています。
表1は近年の主要防災プロジェクトです。令和6年元旦に発生した能登半島地震は記憶が新しいですが、日本は地震だけなく、津波、台風、洪水、土砂災害、豪雨、豪雪と自然災害のリスクに直面しています。日本では政府による取り組みだけでなく一人ひとりの防災意識が高くハード、ソフト両面からの防災が大変進んでいると思います。他国で防災のプロジェクトをする際にも、私が日本人であるとわかると相手政府からよく、日本ではどうしているのかと聞かれます。私はもともと国土交通省や内閣部防災担当で仕事をしていたこともあり、少し鼻高々に日本の取り組みを紹介してしまいます。ただ、社会経済的、行政上の仕組みが異なると日本でとられている施策はそのまま使えないので、相手国の状況を見ながら適切な施策を提案することが大事です。
今後ユネスコで実施している防災のプロジェクトを紹介できればと思いますが、今回は1つだけ、日本の機関を巻き込んだ、AIを活用したプロジェクトを紹介したいと思います。
例えば、ハリケーン、それに伴う水害が発生した際、個人と行政のリスクコミュニケーションはとても大事です。事前にはハリケーン等のより地域に特化した早期警報が避難には必要ですし、災害発生中は避難所の場所等の情報、発生後は必要物資(食料、医療、生活再建サポート)へのアクセスの情報が必要です。しかし緊急事態中に、個人が行政のHP等にアクセスしても必要な情報がすぐに入手できるわけではありません。また行政側も個人の問い合わせ対応にも限界があります。アフリカでは各地で毎年のように水害が発生しており、この状況を改善することを目指し、2020年から2021年まで東アフリカの5か国(ケニア、ルワンダ、南スーダン、ウガンダ、タンザニア)で、AIを使った携帯アプリAIChatbotを開発して、実証実験を行いました。これは、日本の内閣府主催の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)で開発されたAIChatbotをベースにアフリカに合わせたプロトタイプを開発しました。5か国で700名以上の防災に関連する行政関係者を対象にトレーニングを行いました。実際は対象国におけるデータ不足から日本で開発された機能をフルで実装することはできませんでしたが、対象国からは、非常に前向きに受け取れられ現地のメディアにも取り上げられました。現在は、機能充実を図るべく追加資金調達を計画しています。本プロジェクトは、日本の機関であるウェザーニュース、LINE、防災科研からの技術サポートを受けました。
これからもユネスコは特に災害に対して脆弱な地域を対象にサポートを続けていきたいと考えてます。またこの投稿で少しでもユネスコの防災業務について知っていただけると幸いです。もしご質問等あればdrr@unesco.orgまでお問い合わせください。
| テーマ | 対象国および支援国 |
| AI等科学技術を活用した防災 |
|
| 早期警報 |
|
| 建物の強靭化 |
|
| 教育分野の防災 |
|
| 文化財等の防災 |
|
| 自然を基盤とした防災 |
|
| 被災後支援 |
|
| リスクガバナンス |
|
表1 直近の主要プロジェクト(日本の支援によるものを中心に)

図1 AIChatbot プロジェクトの現地でのトレーニングの様子